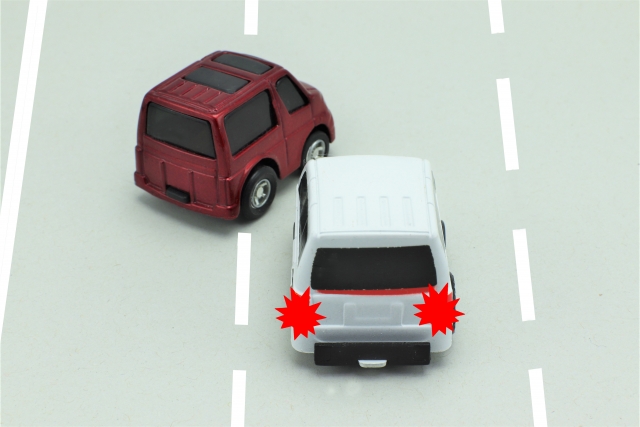2020年6月30日より法改正であおり運転が『妨害運転罪』となり、正式な罰則として明確な罰金や懲役が適用されることになりました。
しかし交通のルールが守れず、我がもの顔で危険行為を繰り返している人は、車を運転しているドライバーだけではありません。
昨今、自転車を運転する人のマナーもかなり低下してしまっています。
2017年5月1日に自転車活用推進法が施行され、2018年6月8日には自転車の活用の推進に関して基本となる『自転車活用推進計画』が閣議決定しましたよね。
『自転車は環境に優しい交通手段であり、健康の増進や混雑の緩和にも役立つ乗り物』
国はこのように認識しているだけに、交通ルールのマナーの悪さが嘆かわしいです。
なので、自転車ドライバーにも厳しい交通ルールが課せられることになりました。
そこで今回は、自転車のあおり運転のルールや厳しい罰則についてまとめました。
あおり運転が自転車にも適用に!危険行為とは
自転車が交通ルールを守れない理由
自転車と自動車・自動二輪が決定的に違うのが、免許証の有無です。
自動車・自動二輪を走行させるためには
・標識や交通ルールを学ばなければならない
・教官の指導の元決められた時間数だけ実践教習を受けなければならない
・卒業試験がある
・運行には免許証が必要
試験に合格しないと、いつまでたっても公道を走ることが許されません。
それに比べて自転車は
・標識や交通ルールを学ぶことが強制されていない
・教官の指導は不要
・卒業試験がない
・自転車の運行は免許制度ではない
幼児の頃に三輪車に乗り、補助輪付きの自転車に乗り、補助輪を外すタイミングでお父さんやお母さんと公園で練習し、あとは自由に乗り回すことができます。
交通ルールを知らなくても、免許証がなくても、自転車に乗れるようになれさえすれば自由に乗り回すことができるのです。
そのことが、自転車が歩行者と同等であると勘違いさせているのではないでしょうか。
○ 自転車は、歩行者と同等ではありません。
○ 自転車は、列記とした車両です。
○ 自転車は、自動車・自動二輪と同等であると認識すべし。
教習所に通う必要がなく、ろくすっぽ交通ルールを教わっていないまま大人になっていくから、「自転車は立場が一番よわいから、何をやってもOK」という勝手な解釈がまかり通っているのです。
これが、自転車が交通ルールを守れない理由です。
自転車の危険行為
2015年6月1日、自転車に対して『危険行為』14項目が制定されました。
これまで危険な乗り方をする人に対して、明確なペナルティを与えることができませんでした。
それが、危険行為として違反内容が具体化したことで、厳しく取り締まることができるようになったのです。
危険行為14項目は以下のとおりです。
・遮断踏切立ち入り
・指定場所一時不停止等
・歩道通行時の通行方法違反
・制御装置(ブレーキ)不良自転車運転
・酒酔い運転
・通行禁止違反
・歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
・通行区分違反
・路側帯通行時の歩行者の通行妨害
・交差点安全進行義務違反等
・交差点優先者妨害等
・環状交差点安全進行義務違反等
・安全運転義務違反
以上の危険行為に、新たに15項目目として加えられるのが『妨害運転』で、2020年7月2日からの施行となります。
危険行為15項目目の妨害運転とは
妨害運転とは、文字通り、他の交通を妨害する行為のことを言います。
要するに『あおり運転』ということです。
自転車だって車両です。
ここまで交通ルールのマナーが悪い、あるいは守れないのであれば、法律として確立し、監視されて然りですよね。
いつまでも「弱い立場です」っていうのは、通用しなくなりました。
そして、法律として制定されてしまう以上、「聞いていない」「知らなかった」という言い逃れはできません。
自分よがりの乗り方を、改めるいい機会かもしれませんね。
妨害運転の7つの行為
妨害運転は、主に以下の7行為が想定されています。
・車・バイク・他の自転車の通行を妨げる目的で、幅寄せ
・車・バイク・他の自転車の通行を妨げる目的で、進路変更
・車・バイク・他の自転車の通行を妨げる目的で、不必要な急ブレーキ
・車・バイク・他の自転車の通行を妨げる目的で、ベルを執拗に鳴らす
・車・バイク・他の自転車の通行を妨げる目的で、車間距離不保持
・車・バイク・他の自転車の通行を妨げる目的で、追い越し違反
状況を想像したらわかりますが、どれも事故を誘発する行為ですよね。
自転車のあおり運転・危険行為は赤切符が切られる?!
自転車の運転者は、次のことが定められています。
『安全に運転をする義務があり、ハンドルやブレーキなどを確実に操作し、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない』
危険行為(15項目)を犯してしまうとどうなるのかというと、
・講習を受けなかったら5万円以下の罰金
これは、14歳以上の人が対象となっています。
「わたしは13歳だから、取締の対象外だもん」と考えるのではなく、自分の命を守るためのルールですので、中学生にあがったタイミングで交通ルールを意識するように心がけましょう。
ということで、安全運転の義務を怠り、悪質な危険行為と判断された場合には赤切符が交付されるようになります。
危険行為に交付される切符
現場の警察官の判断によって、指導・警告にとどまるといったケースもあるのですが、14歳以上の場合は即座に赤切符が切られ、それが3年以内に二回繰り返されると逮捕・書類送検・起訴や裁判を経て懲役刑や罰金などの刑事罰を受けるといった、とても面倒くさい手続きをしなければならない可能性があります。
自動車の交通違反では通常、赤切符と青切符の二種類がありますよね。
・赤切符・・・告知票・免許証保管証(重めの違反に交付される、赤い紙)
・青切符・・・交通反則告知書(軽めの違反に交付される、青い紙)
しかし自転車には軽めの違反切符の青切符は存在せず、切符がきられる時は赤切符となります。
悪質な違反と判断される要因は明確には規定されてはいませんが、例えば警察官の停止命令を無視して逃げたり、事情聴取に応じなかったり、反抗的な態度をとったりすることが挙げられます。
また、自転車には青切符より軽い警告として、黄色の用紙の『自転車指導警告カード』というものがあります。
黄色の用紙は違反の内容が記載されただけのもので、安全講習を受講する義務は発生しません。
青だろうが、赤だろうが、黄色だろうが、警察官に捕まってしまう行為自体を恥だとわきまえるべきですね。
妨害運転の証明
妨害運転は、パトロール中の警察官が現行で行為を確認することがほとんどですが、自動車に設置されているドライブレコーダーの映像が証拠なり摘発されます。
現行犯でなくても、ドライブレコーダーに映像が残ってしまえば赤切符の対象となるのです。
自転車のあおり運転・危険行為!知らなかったじゃすまされない!
現行犯よりも怖いドライブレコーダーの映像。
自分の知らないところで、やらかしてしまった危険行為の映像を警察に提出されてしまえば、「私じゃない」「知らなかった」「わからない」は通用しません。
だって、証拠を突きつけられているのですから。
素直にお縄(赤切符)を頂戴しましょう。
先程もご紹介したとおり、自転車の運転者には安全運転の義務があり、『ハンドルやブレーキなどを確実に操作し、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない』とされています。
街で、良く見かける危険だなと思うのが、雨のときの傘さし運転です。
他にも
・二人乗り
・無灯火走行
・坂道のノーブレーキ
・一旦停止無視
・信号無視
・手放し運転
・安全確認を怠った斜め横断
中でも、携帯電話やスマートフォンを操作しながらの運転は非常に危険です。
片手がふさがった状態で画面に気を取られ、フラフラ蛇行運転は、見ていてハラハラしてしまいます。
繰り返しますが、危険行為の15項目に対して、赤切符二回で安全講習受講の義務が発生します。
妨害運転+信号無視=2回の赤切符で安全講習受講の義務
信号無視+信号無視=2回の赤切符で安全講習受講の義務
どの組み合わせでも、危険行為とみなされ赤切符を2回交付されたら、安全講習を受講しなければならなくなります。
あおり運転が自転車も適用に!法律で決まったルールと罰則が厳しいのまとめ
2019年で、警察が摘発した危険行為の件数は26,687件でした。
そのうち、安全講習を受講した人数が328人でした。
「危険行為ですよ」と摘発されて、「ああ、自分の運転の仕方は危ないんだな」と反省した人が、81人中一人という計算になります。
自転車運行には、免許証制度がありません。
だからどうしても、自転車が車両である事実が欠如してしまいます。
「車道を走っているわけじゃないから」
「歩道だから」
「他の人はルールを守っていないから」
そんな甘えた認識は捨てましょう。
自転車は車両です。
法律上では、自動車や自動二輪車を同じ立ち位置となります。
交通ルールをしっかり守りましょう。